|
10月10日、今日は目の愛護の日だそうな。
視力は1,5健在なので、このまま裸眼でいけたらなぁと思うマイコでございます。 そんなことより!もう10月!!卒論もそろそろまとめに入らなければならぬ時期・・・。 ということで、今日は図書館に篭って論文や資料を探しておりました。 ちなみに私の卒論テーマは『吉備大臣入唐絵巻』に登場する鬼について! 唐に渡ったはいいものの、その奇才を唐の廷臣達から妬まれる吉備真備。 彼らから次々と出される難問を、鬼になった阿倍仲麻呂と共に突破していく・・・! というのがこの絵巻のストーリーです。 これに登場する鬼が可愛くてですね! 今日はその仲麻呂の鬼をちょこっとご紹介~ 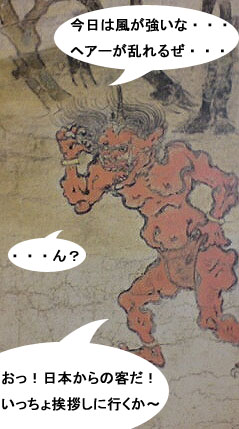 悠々と徒歩で登場。吉備真備がいる楼閣を眺めております 褌一丁の姿は、やはり鬼の定番なのかしらん 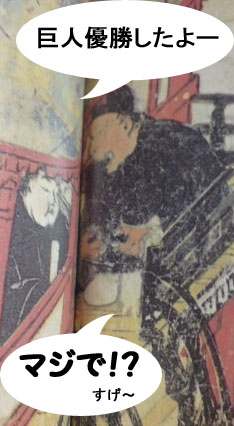 人間の姿になって、吉備真備とご対面~ 日本の話で盛り上がってます 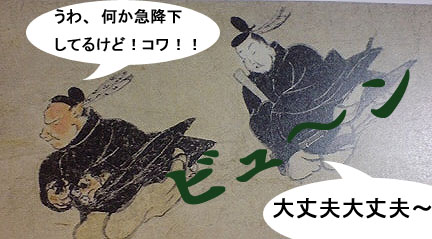 吉備が飛行の術を使い、楼を抜け出しちゃいました! 出された難題「文選」の内容をこっそり聞きに行くのです  柱の影から立ち聞きする一人と一匹。 吉備が聞いてる間、鬼は周りの警護。ナイスタッグ!  今度は囲碁の勝負をすると聞き、吉備のもとへ報告に走る鬼。 もはや吉備の もともと鬼に興味があって、かつ絵巻に登場する鬼を取り扱えたらな~と思ったのが3年の時。 色々な話を読むうちに、人を食べたり襲ったり、敵対するイメージが強かった鬼のイメージを一掃したのがこの鬼でした。 絵巻で描かれている鬼はこの↑の箇所で全部なのですが、どれも表情や仕草がユニークでほんと可愛い! 特に飛んでいる所と柱から覗き込んでいる所がお気に入りです 鬼なのに大した力も使えず、吉備にくっついたままのヘタレなところも好き(笑) 最近強く思ったことだけど、卒論って1年近くかけて作るものだから、やっぱりその調べる対象が好きじゃないと続かない! 私は色々テーマについて悩んで、具体的に「この鬼!」って決まったのが4月辺りだったのですが、でもこうして気に入った作品を調べられるのはすっごく楽しくて充実しています。 ・・・タイムリミットが近いのは自覚してますよちゃんと!ええ!! 画像に台詞をアテレコして妄想してる場合じゃないのもわかってます! 時間も残り少ないですが、いい加減な論文にならぬよう、この視力1,5の脅威のマイコアイを駆使して絵巻の鬼を隅から隅まで暴いていこうと思います!! スパートかけて頑張るぞー!!!
2007,10,10, Wed 21:44
【 文学・語学::中世文学 】 comments (x) trackback (x) |
|
何があったかというと、知り合いからこんなものを頂いちゃったのです
↓↓↓  谷崎潤一郎訳『源氏物語』!! とても古い本なのですが、装丁が凝っていてすっごく素敵☆ しかも、本文には、その巻にちなんだ絵柄が入ってるんですよ~! ↓↓↓  みやびな雰囲気に溢れてます ところで、みなさん、『源氏物語』は読んだことありますか? たぶん、教科書とかで冒頭や、ある一場面なら読んだことがあるって方が多いのではないかと思います。 私が『源氏物語』を全巻通して読んだのは高校を卒業した春休みでした。 それまでに何回かチャレンジはしていたんですけど・・・いつも途中で断念 でも、今度こそは!と決心して、『更級日記』の主人公のように、部屋に籠もって読んでました(笑)とにかく勢いが大事だと思って 全巻読み終わって、「色々な意味で、やっぱり源氏が一番イイ男だった そして、やっぱり不朽の名作だと思いました!何がすごいって、『物語』なのに、完璧なヒーロー・ヒロインを描かなかったことだと私は思っています。 どんなに高い位を持っていても、本当に好きな女性とは結ばれなかったり・・・ 良いこともあれば嫌なこともある。「幸せ」の形は人それぞれ。そういう人間の真実が、平安時代の一人の女性によって書かれたっていうのは本当にすごいことだと思います。 『源氏物語』の魅力なんて、とても一言で語れるものじゃありません。なにしろ、千年たった今でも研究が続いているくらいの作品ですもの(^_^;) だから、時間ができたら、受験生の方は受験が終わったら(苦笑)是非、実際に読んでその魅力を味わってみて下さい 現代語訳された『源氏物語』には、与謝野晶子、円地文子、瀬戸内寂聴、そして谷崎潤一郎のものなど色々あります。それぞれに個性があるので、自分に一番合う本を見つけて、『源氏物語』全巻通読にチャレンジしてみて下さいね☆ 今回は、ついつい源氏について熱くなってしまいました
2007,09,21, Fri 15:54
【 文学・語学::源氏物語 】 comments (x) trackback (x) |
|
今日は大きな地震がありましたね。ちょうど今日の朝は住居学科の友達に「今日、テレビでル・コルビュジェがやるよー」なんてメールをしていたところでした。私の住んでいる所でもかなり揺れましたし、なにより彼女の実家はあちらにあって(大丈夫だったそうですが)、とても不安になりました。上手な言葉が見つかりませんが、ただ、一刻も早く被害に遭われた方々が安らかな夜を迎えられますように、と思います。
7月14日土曜日の朝日新聞(be on Saturday Entertainment)で『和泉式部日記』が特集されていました。和泉式部の恋模様が描かれている作品です。新古今和歌集の演習授業で和泉式部の歌が本歌になっている歌を取り扱ってから、和泉式部にとても興味があるんです。 当然「やったーーー が、なんだかこの特集が薄いような気がする… 不満たらたらでしたが、よく考えてみると、それだけちゃんと勉強しているということなんですよね、きっと。多分!(笑)夏期休暇中の新古今集の課題を私は「中世における和泉式部」としたので、さらに和泉式部を極めようと思います。中世の人々にとって和泉式部という歌人がどのような人物だったか、どのような評価をしていたのか、調べられたらいいなと思います。 ちなみに和泉式部の歌が本歌となっているのは、新古今和歌集の「幾夜われ波にしをれて貴船川袖に玉散る物思ふらむ」(恋歌二・1141 藤原良経)です。和泉式部の歌は是非自分で調べてみてください。どちらもとても魅力的な歌ですよ。
2007,07,16, Mon 23:45
【 文学・語学::中世文学 】 comments (x) trackback (x) |
|
祭の時からそのままになっている枯れた葵。お人形遊びの道具類。二藍や葡萄染めなどのきれじが、ぺちゃんこになって本の中などにはさまっているのを見つけた時。また、おりがおりであったので非常に心を動かされた人からの手紙を、雨など降って所在ない日に、探し出した時。去年使った夏扇。
『新版 枕草子』上巻(石田穣二訳注、角川ソフィア文庫) 今日は本当は博物館めぐりに上野へ行こうかと思っていたのですが、テレビで台風についてのニュースをやっているのを見て「台風が東京を過ぎてからにしよう。それに多分平日のほうが人も少ないし…」 と思い直し(まだ東京には台風が来てないというのに…)、予定変更して読書の日に。 で、読んでいたのは『宮廷女流文学読解考 総論 中古編』(岩佐美代子著、笠間書院)という本。 テスト勉強あるいはレポートの資料とかではなく、まあ卒論でこの辺をやろうかなあ位の気持ちで読んでいたのですが。 すごく面白かったです!岩佐さんは実際に宮仕えを経験された方で、女流日記もその自身の経験にもとづいた論を展開されています。取り上げられている作品を、自分も手にとって読みたいなという気持ちになり、一人で妙にハイテンションになりました(笑) そんなわけで、今回はちょっと冒頭に『枕草子』を引用してみました。 「過ぎにしかた恋しきもの(過ぎ去った頃のことが恋しく思い出されるもの)」として清少納言が挙げているこの部分は、なんてことはない部分ではあるのだけれど、私の好きな章段のひとつです。夏の夕昏時に一人で蝉の声を聞いてるときのような、うまく言えないけどそんな懐かしさと寂しさの入り混じったような気持ちがします。 もうすぐ夏休み。 日本女子大は今年は7/27からですが、中高生の方は来週にはもう休みになるのでしょうか。 普段はできないような、いろんな経験のできる期間です。 後で「過ぎにしかた恋しきもの」といえるような思い出を、たくさん作れるといいですね
2007,07,14, Sat 19:42
【 文学・語学::中古文学 】 comments (x) trackback (x) |
