|
今日、新古今和歌集の演習の授業でレポートを提出したので、だいたい後期の課題が終わってホッとしているところです。
あとはいくつかテストが控えているので、あんまりホッとしてばかりはいられませんが 今年度の授業を振り返ると、この新古今の演習はとても楽しかったなあと思います。 私は今まで中古(平安)文学ばかり、源氏物語ばかり勉強していて、正直和歌の演習(しかも中世)は不安だったんですが、とてもたのしく勉強できました。だって先生が、中世ヨーロッパやらフランス文学やらの話まで持ってきて説明してくださるんです!!メロメロでした(笑) あと、実はこの授業で卒論のテーマである和泉式部に出会えました。いい出会いだったな。 今年度は別の授業で古今集の勉強もできて、和歌を好きになれた年でした。 卒論は中古で書きますが、中世の勉強もして良かったなと思いました。中世のおかげです!なんて調子いいですかね(笑)
2008,01,11, Fri 20:45
【 文学・語学::中世文学 】 comments (x) trackback (x) |
|
10月10日、今日は目の愛護の日だそうな。
視力は1,5健在なので、このまま裸眼でいけたらなぁと思うマイコでございます。 そんなことより!もう10月!!卒論もそろそろまとめに入らなければならぬ時期・・・。 ということで、今日は図書館に篭って論文や資料を探しておりました。 ちなみに私の卒論テーマは『吉備大臣入唐絵巻』に登場する鬼について! 唐に渡ったはいいものの、その奇才を唐の廷臣達から妬まれる吉備真備。 彼らから次々と出される難問を、鬼になった阿倍仲麻呂と共に突破していく・・・! というのがこの絵巻のストーリーです。 これに登場する鬼が可愛くてですね! 今日はその仲麻呂の鬼をちょこっとご紹介~ 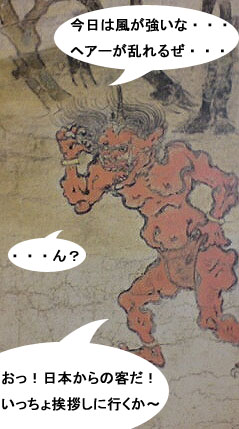 悠々と徒歩で登場。吉備真備がいる楼閣を眺めております 褌一丁の姿は、やはり鬼の定番なのかしらん 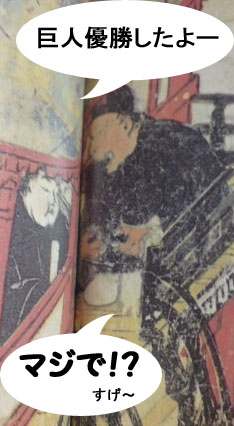 人間の姿になって、吉備真備とご対面~ 日本の話で盛り上がってます 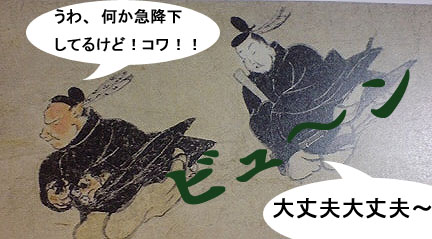 吉備が飛行の術を使い、楼を抜け出しちゃいました! 出された難題「文選」の内容をこっそり聞きに行くのです  柱の影から立ち聞きする一人と一匹。 吉備が聞いてる間、鬼は周りの警護。ナイスタッグ!  今度は囲碁の勝負をすると聞き、吉備のもとへ報告に走る鬼。 もはや吉備の もともと鬼に興味があって、かつ絵巻に登場する鬼を取り扱えたらな~と思ったのが3年の時。 色々な話を読むうちに、人を食べたり襲ったり、敵対するイメージが強かった鬼のイメージを一掃したのがこの鬼でした。 絵巻で描かれている鬼はこの↑の箇所で全部なのですが、どれも表情や仕草がユニークでほんと可愛い! 特に飛んでいる所と柱から覗き込んでいる所がお気に入りです 鬼なのに大した力も使えず、吉備にくっついたままのヘタレなところも好き(笑) 最近強く思ったことだけど、卒論って1年近くかけて作るものだから、やっぱりその調べる対象が好きじゃないと続かない! 私は色々テーマについて悩んで、具体的に「この鬼!」って決まったのが4月辺りだったのですが、でもこうして気に入った作品を調べられるのはすっごく楽しくて充実しています。 ・・・タイムリミットが近いのは自覚してますよちゃんと!ええ!! 画像に台詞をアテレコして妄想してる場合じゃないのもわかってます! 時間も残り少ないですが、いい加減な論文にならぬよう、この視力1,5の脅威のマイコアイを駆使して絵巻の鬼を隅から隅まで暴いていこうと思います!! スパートかけて頑張るぞー!!!
2007,10,10, Wed 21:44
【 文学・語学::中世文学 】 comments (x) trackback (x) |
|
今日は大きな地震がありましたね。ちょうど今日の朝は住居学科の友達に「今日、テレビでル・コルビュジェがやるよー」なんてメールをしていたところでした。私の住んでいる所でもかなり揺れましたし、なにより彼女の実家はあちらにあって(大丈夫だったそうですが)、とても不安になりました。上手な言葉が見つかりませんが、ただ、一刻も早く被害に遭われた方々が安らかな夜を迎えられますように、と思います。
7月14日土曜日の朝日新聞(be on Saturday Entertainment)で『和泉式部日記』が特集されていました。和泉式部の恋模様が描かれている作品です。新古今和歌集の演習授業で和泉式部の歌が本歌になっている歌を取り扱ってから、和泉式部にとても興味があるんです。 当然「やったーーー が、なんだかこの特集が薄いような気がする… 不満たらたらでしたが、よく考えてみると、それだけちゃんと勉強しているということなんですよね、きっと。多分!(笑)夏期休暇中の新古今集の課題を私は「中世における和泉式部」としたので、さらに和泉式部を極めようと思います。中世の人々にとって和泉式部という歌人がどのような人物だったか、どのような評価をしていたのか、調べられたらいいなと思います。 ちなみに和泉式部の歌が本歌となっているのは、新古今和歌集の「幾夜われ波にしをれて貴船川袖に玉散る物思ふらむ」(恋歌二・1141 藤原良経)です。和泉式部の歌は是非自分で調べてみてください。どちらもとても魅力的な歌ですよ。
2007,07,16, Mon 23:45
【 文学・語学::中世文学 】 comments (x) trackback (x) |
|
東京大学の大学院生による、「とはずがたり」の発表を
聞きに行ったときのことです。そのときちょうど私たちが 授業で読んでいた「とはずがたり」。思えば、私たちは 女子大の学生なので、女子の視点からしか読んだこと がなかったのです。それを東大の院生(それも男の人) がどう解釈し、どのように発表するのか、興味津々で 会場へ向かいました。 それにしても東大・・・広いっ!やっとのことでたどり着 いた会場は、 え?ホテルのロビー??ヽ(*゜ω。)ノ 結婚式も行われるという、とても綺麗な建物でした。 実は私、学生同士で行う軽い勉強会のようなものを想 像して行ったので、まずその会場の豪華さにびっくり! (゜Д゜;)ブルブル そしてさらに集まってくる凄そうな人達と、そのわりに 狭い会場がかもし出す圧迫感に、 チキンの私はKO寸前でしたヽ(;´Д`)ノ その凄そうな人達は、実際に凄かったんです! 面白い授業で大人気の教授だったり、私たちが いつも使っている注釈書を書いた人だったり、 授業で読んだ論文を書いたご本人だったり! 「ふぉぉぉー注釈書の人だー。(゜Д゜;) 」 「むひゃーあの論文の人が隣に!(゜Д゜;) 」 終始そんな感じの私。途中でどうして自分が この場所にいるのか分からなくなりました。 「きっ、緊張してきました…。(。☉_☉)」 と一緒にいた院生の先輩に助けを求めると、 「あなたが発表するわけでもないのに?!」 と苦笑されてしまいました。 う、ごもっとも・・・(。☉_☉) そして私の緊張も最高潮に達したところで、発表が 始まりました。テーマは、『とはずがたり論』―父の死 を生きる二条―。 授業では、その父が死んで50日過ぎたあたりだった ので、まさにタイムリー。内容が分かっていると、とても 楽しい!資料の見易さ、発表の分かりやすさはものす ごくて、感動していました。 しかし、ちょっと気になることが一つ。 ・・・・ん?二条って、こんなにけなげでいい人だったっけ? プライドが高くて計算高いしたたかな女二条はどこへ? ∑(゜Д゜)はっ! これが、うわさに聞いていた「男読み」か! 『とはずがたり』には、男の人と女の人によって、その 読み方に違いが現れることがしばしばあるようです。 例えば、男の人が「大人しくて清純そう。」と頬を赤らめ るような人が、女から見たら「どこがー!!計算じゃん!」 と思うことってありますよね?その現象が、この作品を読む 中で現れるということなのです。 つまり、このまじめそうな院生のお兄さんは、 二条に騙されてしまっているー…、と。残念ながら、 そういうことです。 論文の先生にそのことに関して突っ込まれた時にも、 その院生のお兄さんは、「そんなこと考えてもみなか った!」といった顔で聞いていました。その人にとって 二条は、古き良き時代の女、だったのかな、と思いました。 授業でさんざん先生から「二条に騙されてはいけない。」 と言われて読んで、確かに文章の至る所に現れていた 二条の本性。それに気がつかない男の人ってやっぱり いるのか!と、現実を目の当たりにして感動してしまい ました。 女って、男の人が思っているよりもずっと強くてしたたか なんですよ…ね♪(●´艸`) 大学で勉強して物語を読む本当の面白さも知ったけれど、 「物語を読む人を見る」面白さもあるんですね!その人 自身のカラーが見えてくる。発表によって見え方がぼん やりだったり、はっきりだったり…。 そして『とはずがたり』はそれが顕著に現れるので、 とても面白いんだなーと思いました! 大大大満足で帰宅した私。最初の緊張から疲れが出た のか、ご飯を食べてお風呂に入って、その日はすぐに 寝てしまいました。チキンって嫌です、ほんと…。
2006,12,04, Mon 23:49
【 文学・語学::中世文学 】 comments (x) trackback (x) |
