|
夏季休暇が終わり、授業二日目の今日を乗り越えためぐみです。どうもです。
夏季休暇最終日の水曜日、最後の思い出に…ということで! 行ってきました!みなとみらい!! 横浜美術館 「特別展 源氏物語の一〇〇〇年―あこがれの王朝ロマン―」を見に! これは二ヶ月以上前に中吊りで見て、ずぅーと見に行くぞ!と気合を入れていた展示なのです。 しかも、美術館に行く前に学校で割引券があることを確認し、割引料金で入館しました。(皆さんも入学した暁には、是非とも割引券を学校で手に入れて、お得な料金で入館しましょう♪) 開館十分前に着いたというのに、並んでいる並んでいる さすが『源氏物語』というべきでしょうか…千年紀効果?平日なのに、凄い凄い。 配布された「作品展示期間一覧」(横浜美術館 「特別展 源氏物語の一〇〇〇年―あこがれの王朝ロマン―」のHPに「作品展示期間一覧」がPDF形式でダウンロードできます)を見て、授業で使った本があり、胸が高鳴ります。どきどき そうこうしていると、開館のアナウンスが流れ、人は流れていくように中に入っていきました。 展示の内容は…HPを見て頂ければ分かると思いますが、展示は第一章「王朝文化の華・源氏物語の世界」、第二章「源氏物語の系譜」、第三章「生きつづける「源氏物語」」という順番になっており、時代を追って見ることができます。 この記事をご覧になっている高校生の皆さん。 高校生は千円以下で見ることができますので、是非とも見に行って下さいな。 そういうのは、第一章では平安時代に使われていた道具(御櫛、御泔坏(髪の毛を洗う道具)、御台等々)や着物を見ることができるからです! 古典の時間で、出てきた道具や服装が想像できない…という悩みを、美術館に行けば、解決できます!便覧で見るよりもお勧めです。 現に、社会科見学なのか分かりませんが、集団で中学生くらいの子たちがプリントを片手に勉強しに来ていたんです。美術館を通しての古典の勉強でしょうか。よいですね。 皆さんも是非是非 実際に見ると、私も勉強になります。資料に絵が書いてあったり、写真が載っていたりしても、やはり実際に見てみると違いますね。 ほぉ~と、見ながら進み、次の第二章へ行くと…何か置いてあるではありませんか。 何だろうと見ると…!!? なっなんと、小学生・中学生向けの「特別展 源氏物語の1000年 ジュニアブック」というリーフレットが置いてあるではありませんか!? 全体色がピンクの乙女色。可愛らしく、見易く、分かりやすい。これで分かりにくいが為に嫌がられている古典にも興味を持ってもらえるでしょう。 美術館の方の努力に感涙です。小学生ではない私も、勿論手に入れてきました。 小学生の皆さん。中学生以下は無料なので、誰かに頼み込んで連れていってもらってみては如何でしょうか。 因みに、第二章は図屏風が多く、迫力満点です。また、『源氏物語』に魅せられた、各時代の人々が描いた源氏絵がたくさんあるので、飽きることは多分、ないと思います。 そうして、最後の第三章。 ここには、今もなお、生き続けている『源氏物語』の姿を見ることができます。 『源氏物語』は、谷崎潤一郎や与謝野晶子、瀬戸内寂聴さんによって現代語訳され、気軽に読み継がれていますね。また、親しみやすいように漫画になったり(代表なのが、『あさきゆめみし』ですね。因みにアニメ化ポスターも大きく貼ってありました!)しているのも、現代ならではの姿ですよね。 また、『源氏物語』は日本だけではなく、十八の国々の言葉に翻訳され、海外の人にも読まれています。 こういった形で『源氏物語』は今も色々な人達に読まれ、人々を魅了されていくのですね。私も魅了された一人です。 そうして見終わり、『源氏物語』を思う存分、堪能できました。充実した時間でした! ずっと皆さんに勧めていますが、割引券がなくても学生証を見せれば、千円以下で入館できるので、是非とも時間を作って、見に行って下さいな! 充実した時間を過ごすことができること、間違いなしです。 最後に…。 横浜美術館には、cafe小倉山というカフェがあります。 そっそこになんと、特別メニューが?! 詳しくはHPで!
2008,09,26, Fri 22:31
【 文学・語学::源氏物語 】 comments (x) trackback (x) |
|
どうも、一昨日博物館実習を終え、昨日は一日中まるでたれぱんだのようにぐでーっとしていたむとうです。
え?たれぱんだを知らない??いや、きっと今もどこかでよくたれているはずなので、興味のある方は是非ググってあげて下さい。 …何のこっちゃ。 そして、昨日はよくダレていた私ですが、今日はよくかるたしてました…じゃなくて、学校でかるたの練習に参加していました。 諸事情により部長・ともよさんはいなかったのですが、試合をしたり、他のサークルでの合宿の話を聞いたり、札を払う練習をしたり、軽井沢セミナー(通称:軽セミ。日本女子大の学生は必修、夏季休暇中に軽井沢の三泉寮という所へ行く。一年生がこの話題に触れると上級生は必ずといっていいほど「うわー、軽セミとか、もうその言葉自体が懐かしいんだけどぉ!」とか言い出す)の話を聞いたり、「むすめふさほせうつしもゆいちひき」がるた(←の決まり字の札しか使わないで対戦)をしたり、「福田さん辞めちゃうんだってねー」「ホントびっくりですよねー」という世間話をしたり、「あ」がるた(「あ」で始まる決まり字の札しか使わない。とてもつらい)をしたりと、まったり楽しく過ごしました。 思いつくままに書いていたら、とても読みづらい文に。 まあ重要なのは、一年生って可愛いよね、って所です。テストには出ないけど重要なポイントです。 …何のこっちゃ。 そんなこんなで練習後、札とカセットを部室へ運び、一人ぼんやりしていたところ。 「あれっ、むとう先輩?!」 台湾から帰ってきて、今日は学校で司書教諭の集中講義をうけていためぐみちゃんと遭遇。部室で二人、久しぶりに話をしました。 何の話をしたかというと、まあ一番はやっぱりお互いの実習の話だったのですが、気がついたら↓な話題に突入。 むとう「そういえば『あさきゆめみし』アニメ化するらしいよ!!」 めぐみ「えぇーっ、ホントですか?!えっ、それってやっぱり深夜ですか??」 むとう「フジテレビでノイタミナってあるじゃん。あの枠で来年1月から放送するらしいよー」 めぐみ「ああ、あれですか。やっぱり深夜なんですね。千年紀だからってことですかね」 むとう「なんかもう、千年紀こわいねー。この勢い、いつまで続くんだろう」 めぐみ「そうですね…っていうか、来年1月からやるんなら、それってもう千年紀じゃなくて千一年紀ですよね?」 むとう「!!た、確かに…」 めぐみちゃんは今日も冴えていました。 でも、今思い出しながら書いていて気づいたんだけど、めぐみちゃんは深夜枠かどうかを気にしすぎじゃないかな(笑) いや確かにあんなお話をゴールデンタイムにやられても困っちゃう訳ですが…。 よし、妙に綺麗にまとまった。でも、源氏物語の話はちょろっとしかしてないぞ(笑)
2008,09,02, Tue 19:44
【 文学・語学::源氏物語 】 comments (x) trackback (x) |
|
以前にもこのブログに書いたことがあるのですが、「自主ゼミ」というのは、単位にならないけれど勉強したい仲間が自主的に集まって活動する勉強サークルのようなものです。現在「自主ゼミ」は上代・中古・近世・近代・漢文・日本語の6つのゼミが活動しています。ゼミの活動はそれぞれですが、先生の近くでアドバイスをして頂きながら勉強できるのが大きな魅力の一つです。
今日は、実際に私が参加している上代自主ゼミの活動の一部をご紹介させて頂こうと思います。上代自主ゼミは、週一回50分の昼休みを利用して本居宣長の『古事記伝』を読んでいます。この『古事記伝』実は去年から三之巻を読み続けているんですが、10ページ程しか進んでいないんです。 「天地初めて発けし時、高天原に成りし神の名は、天之御中主神、次に高御産巣日神、次に神産巣日神。この三柱の神は、みな独神と成りまして、身を隠したまひき」 (『古事記』(上) 次田真幸 講談社学術文庫) 上記の部分の解説がまだ読み終わっていないという状況です。何となく『古事記伝』の長さを想像できるのではないでしょうか。私が卒業するまでには読み終わらないだろうと想いつつも、毎回ちょっとづつ読み続けています。 普段の活動は、その場で意味を考えて訳しながら読むのですが、自主ゼミの活動はそれだけではありません。昨年度・今年と上代自主ゼミでは夏休みに文学散歩を企画して、行っています。 今年度の上代自主ゼミ文学散歩は、『万葉集』に詠われた真間の手児奈の縁の地である千葉県市川市で行うことになり、一昨日、8月5日に行ってきました。行程は以下の通りです。 ①JR市川駅集合→②市立市川考古博物館→③堀之内貝塚→④下総国分寺跡→⑤手児奈霊堂 さて、皆様。一昨日、どのような天気だったか覚えていらっしゃいますでしょうか? そう。5日は関東で大雨が降った日だったのです。 文学散歩を始めた頃は曇っていただけだったのですが、考古博物館を出る頃になってザーット雨が降り出し、雷の音が遠くでするなあ。と思っていたらいきなり近くでバリバリ・ゴロゴロと、大きな音と雷の音がして雨脚はどんどん強まっていくのです。道路がまるで小川のように水だらけになっている中を、文学散歩。ある意味、ものすごく強烈でした。 下総国分寺に行くまでには、靴は水浸しで服もびしょぬれ。もちろん傘をさしていたのですが、それはかろうじて髪が濡れるのを防いでくれただけでした。 下総国分寺跡では、礎石が残っているものを見たり、瓦の文様に注目して見学しました。 ここまでが午前中の文学散歩でした。 お昼を食べて、午後は手児名霊堂とその周りを散策しました。 「真間の手児名」は複数の男性に求婚されて悩んだ末入水した女性として『万葉集』に詠われています。 ここからは、いくつかの歌と、文学散歩の写真を一緒に載せてみます。 『万葉集』巻九 1808番 勝鹿の 真間の井見れば 立ち平し 水汲ましけむ 手児名し思ほゆ ≪真間の井≫↓   『万葉集』巻十四 3387番 足の音せず 行かむ駒もが 葛飾の 真間の継橋 やまず通はむ ≪真間の継橋≫↓  最後に、文学散歩に際してゼミの後輩が大学院の先輩に指導していただきつつ、作ってくれた「文学散歩の栞」の写真と、皆で食べた甘味屋さんのクリーム餡蜜の写真です。  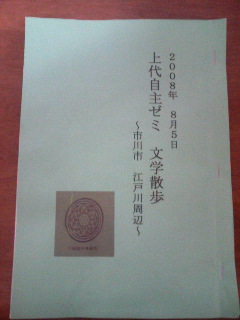 一日かけて、先生に御講義いただきつつ様々な史跡をめぐることができてとても楽しかったです。皆で食べた甘味も美味でした。 大雨と、雷と、文学散歩。 決して一生忘れないだろう、大学三年生の夏の思い出になりました
2008,08,07, Thu 23:11
【 文学・語学::上代文学 】 comments (x) trackback (x) |
|
昨日は蛍を見に行ってきました。
去年も渋谷の植物園に見に行ったのですが、今年は目黒のに行ってきました。都会で蛍が見れるのは、なんだか贅沢な気分です。 蛍は古典文学の中にも多く登場し、親しみ深い虫でもあります。 有名なのは、源氏物語・蛍巻の玉鬘の場面。源氏の放った蛍によって玉鬘の美しさが男の目に触れる、そんな場面です。自分の養女(玉鬘)をわざと男の目に触れさせるなんて、源氏がひどく大胆で、またいやらしい感じがします。でもそこで描かれる蛍のおかげで、読む側には何よりも優雅な印象が強く残るのです。 ちなみに、和泉式部にも有名な蛍の歌があるんですよ。 これらの作品に登場する蛍は、日本固有の種である源氏蛍でしょう。体も発する光も大きい蛍です。 でも今回見たのは、小さい平家蛍。源氏蛍とはまた違った雰囲気で、やっぱり古典には源氏蛍が似合うけれど、これはこれで綺麗だなと思います。そして何より、この季節にしか出会えない嬉しさを感じました。 帰りにハロハロを食べて、ばっちり夏を満喫した日でした。
2008,07,22, Tue 18:29
【 文学・語学::中古文学 】 comments (x) trackback (x) |
