|
以前にもこのブログに書いたことがあるのですが、「自主ゼミ」というのは、単位にならないけれど勉強したい仲間が自主的に集まって活動する勉強サークルのようなものです。現在「自主ゼミ」は上代・中古・近世・近代・漢文・日本語の6つのゼミが活動しています。ゼミの活動はそれぞれですが、先生の近くでアドバイスをして頂きながら勉強できるのが大きな魅力の一つです。
今日は、実際に私が参加している上代自主ゼミの活動の一部をご紹介させて頂こうと思います。上代自主ゼミは、週一回50分の昼休みを利用して本居宣長の『古事記伝』を読んでいます。この『古事記伝』実は去年から三之巻を読み続けているんですが、10ページ程しか進んでいないんです。 「天地初めて発けし時、高天原に成りし神の名は、天之御中主神、次に高御産巣日神、次に神産巣日神。この三柱の神は、みな独神と成りまして、身を隠したまひき」 (『古事記』(上) 次田真幸 講談社学術文庫) 上記の部分の解説がまだ読み終わっていないという状況です。何となく『古事記伝』の長さを想像できるのではないでしょうか。私が卒業するまでには読み終わらないだろうと想いつつも、毎回ちょっとづつ読み続けています。 普段の活動は、その場で意味を考えて訳しながら読むのですが、自主ゼミの活動はそれだけではありません。昨年度・今年と上代自主ゼミでは夏休みに文学散歩を企画して、行っています。 今年度の上代自主ゼミ文学散歩は、『万葉集』に詠われた真間の手児奈の縁の地である千葉県市川市で行うことになり、一昨日、8月5日に行ってきました。行程は以下の通りです。 ①JR市川駅集合→②市立市川考古博物館→③堀之内貝塚→④下総国分寺跡→⑤手児奈霊堂 さて、皆様。一昨日、どのような天気だったか覚えていらっしゃいますでしょうか? そう。5日は関東で大雨が降った日だったのです。 文学散歩を始めた頃は曇っていただけだったのですが、考古博物館を出る頃になってザーット雨が降り出し、雷の音が遠くでするなあ。と思っていたらいきなり近くでバリバリ・ゴロゴロと、大きな音と雷の音がして雨脚はどんどん強まっていくのです。道路がまるで小川のように水だらけになっている中を、文学散歩。ある意味、ものすごく強烈でした。 下総国分寺に行くまでには、靴は水浸しで服もびしょぬれ。もちろん傘をさしていたのですが、それはかろうじて髪が濡れるのを防いでくれただけでした。 下総国分寺跡では、礎石が残っているものを見たり、瓦の文様に注目して見学しました。 ここまでが午前中の文学散歩でした。 お昼を食べて、午後は手児名霊堂とその周りを散策しました。 「真間の手児名」は複数の男性に求婚されて悩んだ末入水した女性として『万葉集』に詠われています。 ここからは、いくつかの歌と、文学散歩の写真を一緒に載せてみます。 『万葉集』巻九 1808番 勝鹿の 真間の井見れば 立ち平し 水汲ましけむ 手児名し思ほゆ ≪真間の井≫↓   『万葉集』巻十四 3387番 足の音せず 行かむ駒もが 葛飾の 真間の継橋 やまず通はむ ≪真間の継橋≫↓  最後に、文学散歩に際してゼミの後輩が大学院の先輩に指導していただきつつ、作ってくれた「文学散歩の栞」の写真と、皆で食べた甘味屋さんのクリーム餡蜜の写真です。  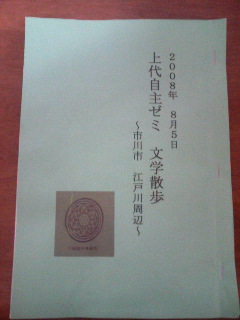 一日かけて、先生に御講義いただきつつ様々な史跡をめぐることができてとても楽しかったです。皆で食べた甘味も美味でした。 大雨と、雷と、文学散歩。 決して一生忘れないだろう、大学三年生の夏の思い出になりました
2008,08,07, Thu 23:11
【 文学・語学::上代文学 】 comments (x) trackback (x) |
NEW ENTRIES
ブログ移転のお知らせ (04/01)
私の母校は日本女子大学 (03/31)
「愛しています。」 (03/30)
ポスター♪ (03/29)
世界は広がっていくわけで (03/28)
春休みの過ごし方 (03/27)
たまの休憩 (03/26)
明日のために今日がある! (03/25)
『野馬台の詩』 (03/24)
★ブログ部お食事会★ (03/23)
私の母校は日本女子大学 (03/31)
「愛しています。」 (03/30)
ポスター♪ (03/29)
世界は広がっていくわけで (03/28)
春休みの過ごし方 (03/27)
たまの休憩 (03/26)
明日のために今日がある! (03/25)
『野馬台の詩』 (03/24)
★ブログ部お食事会★ (03/23)
CATEGORIES
がんばれ受験生! (29件)
日常生活 (745件)
└ 食 (28件)
└ かるた (31件)
└ 一人暮らし (13件)
└ 寮生活 (15件)
└ 家族・友人 (15件)
└ ファッション・メイク (8件)
└ 高校時代 (7件)
└ イベント・年中行事 (10件)
大学生活 (620件)
└ サークル活動 (42件)
└ アルバイト (21件)
└ 美術館・博物館 (29件)
└ 旅行 (44件)
└ 履修・単位関係 (22件)
└ 卒業論文 (30件)
└ 教職関連 (30件)
└ 司書・司書教諭 (3件)
└ 日本語教育 (5件)
└ 映画・舞台鑑賞 (24件)
└ 目白祭 (18件)
└ 自主ゼミ (2件)
就職活動 (37件)
国語国文学会 (14件)
読書 (17件)
文学・語学 (43件)
└ 源氏物語 (4件)
└ 上代文学 (9件)
└ 中古文学 (6件)
└ 中世文学 (7件)
└ 近世文学 (1件)
└ 近代文学 (5件)
└ 現代文学 (1件)
└ 中国文学 (4件)
└ 日本語学 (3件)
雑感 (60件)
LOVE (21件)
それぞれのクリスマス (42件)
新年 (23件)
日文HPリニューアル (6件)
日常生活 (745件)
└ 食 (28件)
└ かるた (31件)
└ 一人暮らし (13件)
└ 寮生活 (15件)
└ 家族・友人 (15件)
└ ファッション・メイク (8件)
└ 高校時代 (7件)
└ イベント・年中行事 (10件)
大学生活 (620件)
└ サークル活動 (42件)
└ アルバイト (21件)
└ 美術館・博物館 (29件)
└ 旅行 (44件)
└ 履修・単位関係 (22件)
└ 卒業論文 (30件)
└ 教職関連 (30件)
└ 司書・司書教諭 (3件)
└ 日本語教育 (5件)
└ 映画・舞台鑑賞 (24件)
└ 目白祭 (18件)
└ 自主ゼミ (2件)
就職活動 (37件)
国語国文学会 (14件)
読書 (17件)
文学・語学 (43件)
└ 源氏物語 (4件)
└ 上代文学 (9件)
└ 中古文学 (6件)
└ 中世文学 (7件)
└ 近世文学 (1件)
└ 近代文学 (5件)
└ 現代文学 (1件)
└ 中国文学 (4件)
└ 日本語学 (3件)
雑感 (60件)
LOVE (21件)
それぞれのクリスマス (42件)
新年 (23件)
日文HPリニューアル (6件)
ARCHIVES
CALENDAR
LINK
PROFILE
管理人(1)
あい(74)
あやの(54)
ササキ(31)
ヤマザキ(38)
なつみ(48)
しおり(26)
あむ(78)
ともよ(96)
ぐんじ(37)
ともみ(63)
めぐみ(97)
なおこ(37)
まいこ(49)
むとう(77)
あゆみ(86)
もえ(83)
ゆきこ(30)
ちこ(74)
あさみ(57)
なな(76)
あやこ(64)
たまき(55)
みかこ(56)
あずさ(24)
あゆ(21)
さやか(46)
ゆうこ(21)
ともこ(22)
まり(22)
まゆ(19)
まなみ(19)
わか(21)
れい(13)
かずえ(15)
しほ(5)
あい(7)
みどり(3)
ゆり(5)
さと(3)
なお(4)
あい(74)
あやの(54)
ササキ(31)
ヤマザキ(38)
なつみ(48)
しおり(26)
あむ(78)
ともよ(96)
ぐんじ(37)
ともみ(63)
めぐみ(97)
なおこ(37)
まいこ(49)
むとう(77)
あゆみ(86)
もえ(83)
ゆきこ(30)
ちこ(74)
あさみ(57)
なな(76)
あやこ(64)
たまき(55)
みかこ(56)
あずさ(24)
あゆ(21)
さやか(46)
ゆうこ(21)
ともこ(22)
まり(22)
まゆ(19)
まなみ(19)
わか(21)
れい(13)
かずえ(15)
しほ(5)
あい(7)
みどり(3)
ゆり(5)
さと(3)
なお(4)
LOGIN
現在のモード: ゲストモード
POWERED BY
SEARCH
QR code
